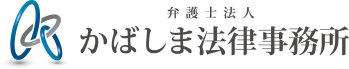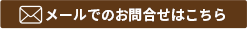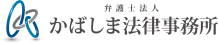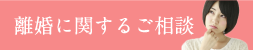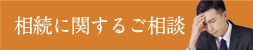弁護士コラム
相続財産の調査
相続に争いがある場合はもちろん、争いがない場合にも相続財産がどこに何がどれだけあるのかを把握することは遺産分割の前提となります。
たとえ、相続人が1人で遺産分割の必要がない場合でも、被相続人(故人)にどのような財産、負債がないかわからない場合は、相続財産の調査が必要な場合があります。
1 相続財産の種類
財産は、プラスの財産とマイナスの財産(負債、借金)があり続きを読む >>
遺言執行者の権利義務
1遺言執行者の立場
遺言執行者は、遺言者に代わって、遺言の内容を実現するために必要な事務処理を執り行います。
遺言執行者は、必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではありません。
例えば、事実婚の場合の妻は相続人ではありませんが、遺産の一部または全部を事実婚の妻に遺贈(遺言により財産の一部または全部を与えること)をした場合は、その結果相続人が相続する遺産が減少することになります。続きを読む >>
顧問先企業に向けた、コロナ対策セミナーを実施しました。
みなさんこんにちは。弁護士の泊祐樹です。
令和2年7月17日(金)に、当事務所の顧問先企業の方々に向けて、「ウィズコロナ時代の新しい労務様式」と題して労務セミナーを開催させていただきました。
テーマは、①コロナと休業手当、②コロナと解雇、③コロナと業務命令、それから④テレワークの具体的な運用方法や労務問題、です。
具体的な事例などを用いたご説明させていただきました。ありが続きを読む >>
新型コロナウイルスに関するQ&A第2弾(労務問題について)
前回、新型コロナウイルスに関するQ&A第1弾を掲載しましたが、今回はその第2弾です。
おそらくは全ての業種の方々が、今般の新型コロナウイルスによる直接・間接の影響を受けているのではないかと思います。
少しでもお役に立てる情報を提供して参りたいと思いますので、ご覧ください。
Q 新型インフルエンザ等対策特別措置続きを読む >>
就業規則に関するQ&A
〈就業規則の作成・届出義務〉
Q1.当社の事業所では、正社員が7名、パートタイマーが5名います。就業規則を必ず作成しなければならないでしょうか?
A.常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出義務があります。
(解説)
労働基準法89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定事項について就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署になります)続きを読む >>
敷金規定の新設について-債権法改正対応シリーズ賃貸借その3-
Q 敷金の規定とは何ですか。
A 改正により、敷金の定義が明文化されました。
敷金とは、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」(民法622条の2第1項)という定義が民法上に記載されるに至りました。
賃貸人が取得した敷金は、賃貸借契約が終了し賃借続きを読む >>
原状回復に関するルールについて-債権法改正対応シリーズ賃貸借その2-
Q 原状回復義務に関するルールとはなんですか
A 賃貸借契約の終了の効果として、賃借人の原状回復義務が明文化されました。原状回復とは、借りていた物件について借りたときの状態に戻すことをいいます。また、原状回復の範囲が明確化されました。まず、原状回復の対象になる「損傷」について、通常の使用収益によって生じた損耗と経年変化による損耗が除外されました。また、賃借人の帰責事由続きを読む >>
利息(民法改正による法定利率の変化)
Q 今回の民法改正によって法定利率はどのようにかわりますか?
A
1 当初の利率を3%とした変動利率制となります
旧民法においては、年5%の固定金利とされていましたが、新法においては3年を一期
とした変動制が採用されました。当初の利率は3%として3年を一期とし、一期ごとに法
定利率の見直しを行うこととなりました。
2 変動制続きを読む >>
協議による時効の完成猶予(民法改正)
Q 改正法において新設された「協議による時効の完成猶予」(新民法151条)とは、どのようなものですか?
A 1 意義
「協議による時効の完成猶予」とは、権利に関する協議を行う旨の合意を書面で行った
場合、①その合意があった時から1年を経過した時、②その合意において当事者が協議を
行う期間(1年に満たないものに限る)を定めた場合にはその期間を経過した時、③当事続きを読む >>
債権法改正 時効
Q 消滅時効の期間が改正されたと聞きました。具体的にはどのように変わったのですか?これまでの契約により発生している債権についても改正法が適用されるのでしょうか?
A 原則として、「債権者が権利を行使することを知った時」(主観的起算点といいます)から5年、「権利を行使することができる時」(客観的起算点といいます)から10年となりました。施行日である2続きを読む >>