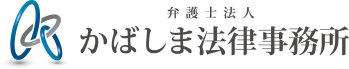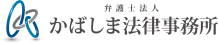弁護士コラム
遺言書の効力
「父が他界しました。父と同居している兄が父が書いた遺言があり、父の財産のほとんどが兄に相続する、と書かれていました。しかし父はここ5年くらい認知症を患っており、遺言の日付は4年前で、その当時は認知症が結構進んでいたと記憶しております。」
遺言書の効力が問題となる場合は、大きく分けて2つあります。

1つ目が、法に定められた形式を満たしているのか、という形式的な問題
もう1つが、遺言をする時点で遺言者(被相続人)に遺言をする能力があったのかという問題です。
1 遺言書が発見されたら
封がされているのであればそのままにして、家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。封がされていなくても、決して書き込みなどはせずにそのままの状態で検認の手続きを行うようにしてください。
検認の手続きについて、ご不明な点がありましたら、弁護士にご相談してください。
2 形式的な問題について
遺言は法が定めた形式に従って書かれていないと無効になります。
遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書と特別の方式によるものがあります。
形式が問題となるのは、自筆証書が多くなっています。
自筆証書遺言は、何も準備をすることなく、遺言をすることができるので、多く利用されています。しかし、遺言をする方は、法が定めた形式を十分に知っているとは限りませんし、さらには、法が定めた形式を満たしていない場合は無効になることも知らない場合があります。
例えば、日付に令和2年6月吉日と書いた場合は無効になります(吉日では何日か不明)。
また、原則として全文を自筆で書かなければなりません。途中の誤りも訂正の方式を厳密に守らなくてはならないのです。また、連名の遺言は無効になります。
このように、自筆証書遺言は作成する際に形式を満たしておらず、無効になる場合が多くあります。
形式的な問題により無効となるのを防ぐためには、公証人が関与して作成された公正証書によることをお勧めします。
3 遺言能力の問題
遺言は、遺言者が遺言をする時点で遺言の趣旨を理解して、自らの意思を表明する能力がなければなりません。これを「遺言能力」と言います。
遺言能力は15歳以上のものであれば基本的にあるとされています。しかし、認知症が進み、自ら意思を表明する能力が失われた場合は、遺言をすることができません。そして、そのような状態で作成した遺言は無効となります。
例の場合は、父の認知症が進んでいるので、遺言をする能力(遺言能力)が失われている可能性があります。兄が父の認知症を認めて、遺言が無効であることを前提に法定相続での遺産分割に応じれば、遺産分割協議(遺産分割についての話し合い)を行って遺産を分割することになります。
兄が遺言の有効性を争うなら、遺言無効確認の裁判をすることになります。
裁判では、父が遺言をした時の遺言能力が有るかどうかが判断されます。病院に入院・通院してた場合は、カルテ、診断書、介護保険の申請をしていた場合は要介護判定の資料、その他、当時の判断能力がわかる資料を証拠に遺言能力がないことを立証することになります。
このように、遺言能力の争いになると双方かなり大変な裁判になることが予想されるので、第三者の専門家である公証人が立ち合い遺言の内容を確認する、公正証書での遺言の作成をお勧めします。
遺言について疑問がある場合は、弁護士へご相談ください。
以上